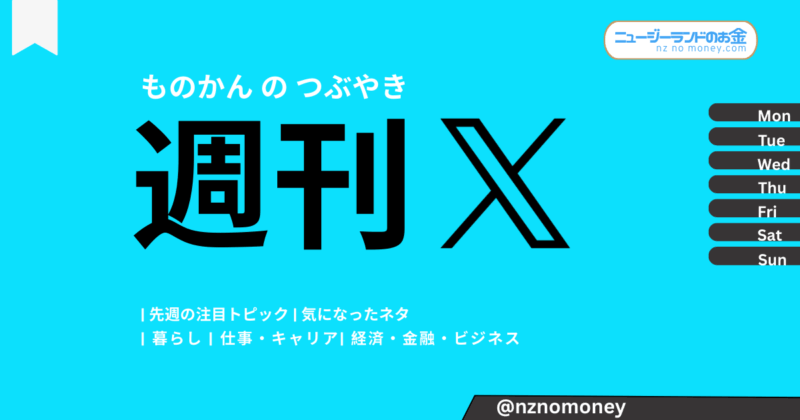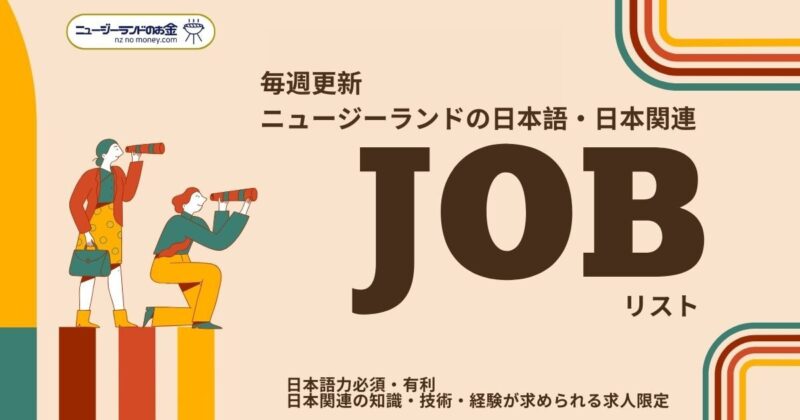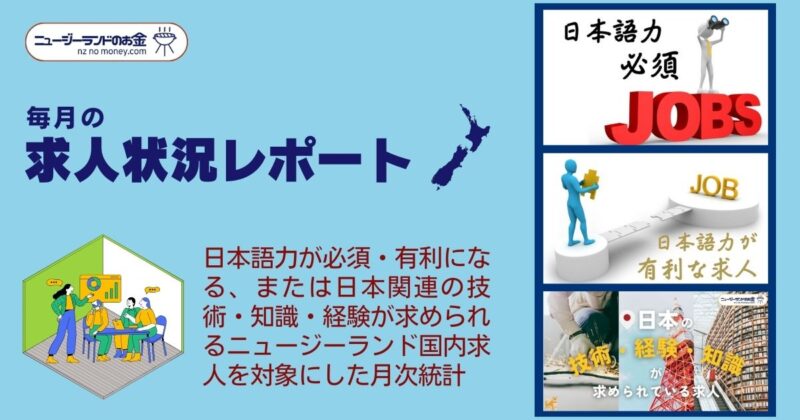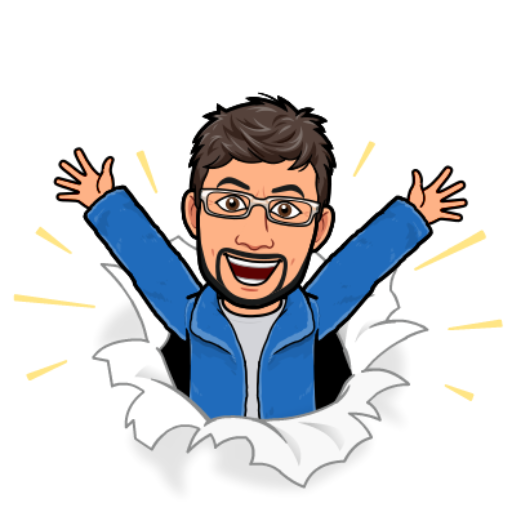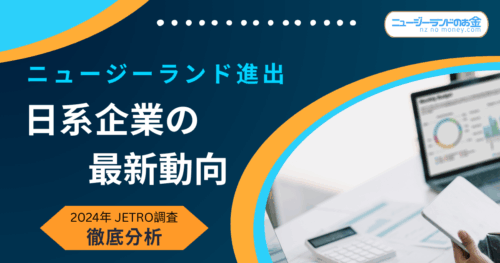【徹底分析】ニュージーランド進出日系企業の最新動向(2024年 JETRO調査)
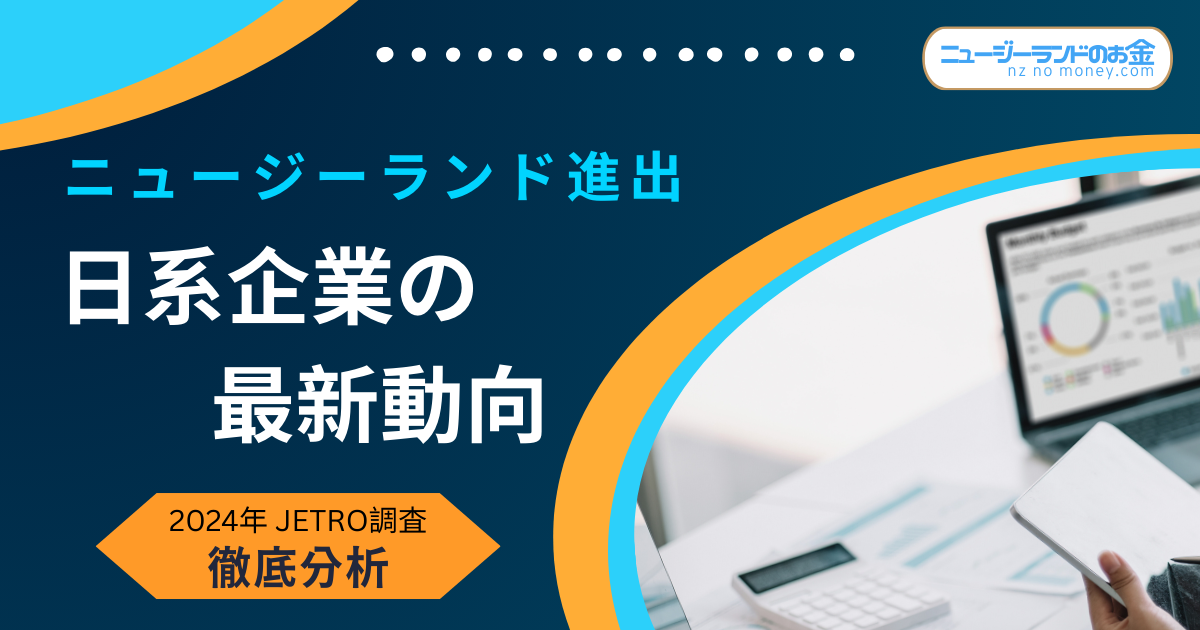
2024年11月末に日本貿易振興機構(JETRO)が発表した「海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)」の中から、ニュージーランド(NZ)進出企業の実態を深掘りします。
結論から言えば、NZ進出日系企業は「短期利益型」ではなく「ローカル密着・堅実経営型」の特徴が顕著に表れていました。
この記事では、データに基づき NZ市場の本質と今後の事業機会を深堀りします。
進出企業数と業種構成 ― 小規模だが堅実な市場
今回の調査報告書によるとNZに進出している日系企業は 167社。そのうち 42社(内訳:大企業24社、中小企業18社)、回答率25.1%が今回の調査に協力したようです。
 ものかん
ものかんニュージーランドの回答率は調査対象19カ国中、24.6%で最下位のタイに次いで低い値でした。任意回答とはいえ、もう少し協力姿勢が欲しかったなというのが率直な感想。
業種構成は以下の通り:
- 製造業:14社(33.3%)
- 非製造業:28社(66.7%)
非製造業(卸売・小売、サービス業)の比率が高い理由は、NZが人口530万人の小規模経済市場であるため「ローカル生産拠点」としての魅力よりも、 輸出・流通・サービス業拠点としての魅力がより高いと見る事が多いためです。
分析ポイント
– NZは「作る場所」より「売る場所」・「サービスを提供する場所」
– 特に食品・教育・観光・ITサービス分野で日系企業の親和性が高く、また近年は宇宙航空関連分野における日系企業との連携もみられている。
営業利益状況 ― 黒字率46.3%
NZで回答した企業の 46.3%が2024年の営業利益見通しを「黒字」と答えており、豪州および調査対象全体と比べても厳しい黒字見通し率であることが分かります。
| 地域 | 黒字 | 均衡 | 赤字 |
|---|---|---|---|
| NZ | 46.3% | 26.8% | 26.8% |
| 豪州 | 76.2% | 15.6% | 8.2% |
| ASEAN | 65.2% | 17.7% | 17.1% |
| 全対象 | 65.8% | 17.5% | 16.7% |
他国・地域と比較すると黒字率が低く、魅力に欠けるように映りますが、NZ市場の真髄は短期的な爆発的成長は乏しいが、中長期的な堅実黒字を出しやすい市場であることです。
NZ国内に目を向けて前年と比較すると、顕著なインフレに見舞われ、中央銀行が積極的な利上げを継続実施して経済活動も鈍化しGDP成長率もマイナスを記録するなど、景気減速が明らかな状態で、NZに進出している日系企業の営業見込みは黒字率と赤字率ともに減少して「均衡」が倍増しているのが分かります。この均衡の増加は、裏を返せば、経済が回復基調に戻れば、再び黒字化する可能性を秘めた企業が多いとも言えます。
| 見込み | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|
| 黒字 | 46.3% | 52.5% |
| 均衡 | 26.8% | 12.5% |
| 赤字 | 26.8% | 35.0% |
 ものかん
ものかん中長期的な堅実黒字を出しやすい市場という見方なら、2024年は逆風のなか無理してリソースを投入せず「損益均衡」で良しとする企業の割合が多かったといえるかもしれません。
企業マインドDI ― 前向きな見通し
景気判断の楽観度合いといえる「景況感DI」は
2024年:7.3ポイント → 2025年:31.7ポイント と大幅に改善しています。
 ものかん
ものかん平時であれば堅実な黒字を出しやすいNZ市場において、2024年はインフレが大幅に鈍化し経済の不確実性が和らいだことで、コスト抑制や景気回復による売上増への期待が高まりました。
加えて、RBNZ(ニュージーランド準備銀行)の利下げによる借入コストの軽減や投資促進への期待も企業心理を後押ししたと考えて良いと思います。さらに、雇用市場が売り手市場から買い手市場へと転じたことで、人件費高騰をリスクと捉えていた企業の安心感につながったことも、楽観的な見通しを支える要因と言えるかと思います。
注意点として「景況感」はあくまでも企業の心理や期待を示すもので、「実際の経済状況」を示すものではない事は理解しておいてください。
事実、直近の4月末にANZBankが発表した景況感指数ではトランプ関税に端を発した世界経済の混乱が悪影響となり9ヶ月ぶりの低水準に低下しています。
今後1~2年の事業展開 ― ローカル市場志向の拡大へ
NZ進出している日系企業の2025-26年にかけての事業を展開する意向をみると、ここでもNZ市場の特徴を表す数値がみてとれます。
| 意向 | 割合 |
|---|---|
| 事業拡大予定 | 21.4% |
| 現状維持 | 73.8% |
| 縮小・撤退 | 4.8% |
海外に進出しておいて「現状維持」が突飛しているのは他国・地域と比べても特異な形。
「小規模だが堅実な市場」という印象を強める数値と言ってよいかと思います。
 ものかん
ものかん企業の「現状維持」志向は「小規模だが堅実」というニュージーランドの市場特性と結びついており、安定性と持続可能性を重視する企業にとって、ニュージーランドをより魅力的な進出先の一つにしていると思います。
とはいえ20%強が「事業拡大」を意識しており、その拡大理由トップ3がこちら。
1:ローカル市場ニーズの拡大:55.6%
2:輸出増加:33.3%
3:高付加価値製品・サービスへの受容性が高い:22.2%
 ものかん
ものかんニュージーランドに進出している日系企業の多くが非製造業であり、事業拡大を意識している層の過半数がローカル市場ニーズの拡大を狙っているという事実は、ローカライズ戦略が重要であることを示唆しており、
ニュージーランドの文化や、習慣、消費者の嗜好に合わせた事業展開が成功の鍵となります。
つまり単に日本や他国で成功したビジネスモデルをニュージーランドに持ち込むのではなく、ニュージーランドに最適化させることで持続的な成長を目指す姿勢と捉えてよいかと思います。
競合相手の数 ― ニュージーランド市場、驚きの安定性
他国・地域と比較してNZが圧倒的な「横ばい」率を見せているのが、5年前(2019年)と比較した競合相手数の増減。
| 地域 | 増加 | 横ばい | 縮小 |
|---|---|---|---|
| NZ | 20.0% | 80.0% | 0.0% |
| 豪州 | 37.0% | 58.7% | 4.3% |
| ASEAN | 46.5% | 49.6% | 3.9% |
| 全対象 | 48.6% | 47.7% | 3.7% |
NZではなんと8割もの企業が「競合相手の数に変化なし」と回答。
新たなライバルが続々と参入してきて競争が激化し、企業が淘汰されながら市場が成長していくという、一般的な経済のセオリーとは一線を画しています。
 ものかん
ものかんこの「横ばい」率は、NZ市場が外部からの影響を受けにくく、既存のプレーヤーが安定した地位を築きやすいことを示唆しています。
激しい競争にさらされることなく、じっくりと顧客を育て、安定した収益を確保しやすい。
つまり、もう何度も書いていますが「爆発的成長は乏しいが、中長期的な堅実黒字を出しやすい市場」なのです。
ニュージーランド進出 - 環境上のメリットとリスク
NZに進出している日系企業が「環境上のメリット」としている点と、目を背けることのできない「リスク」に付いて複数回答したものをまとめました。
| メリット | リスク |
|---|---|
| 安定した政治・社会情勢 | 人件費の高騰 |
| 整備された法制度、明確な運用 | 労働力の不足・人材採用難(専門・技術職・中間管理職等) |
| 言語・コミュニケーション情報障害の少なさ | 労働力の不足・人材採用難(一般ワーカー・スタッフ・事務員等) |
| 電力インフラの充実 | 自然災害 |
| 駐在員の生活環境が優れている | 従業員の離職率の高さ |
 ものかん
ものかんこれらの回答を見ると、ニュージーランドは事業の安定基盤という点で優位性を持つ一方で、労働力確保と人材定着という課題、そして自然災害への備えが重要なポイントとなる市場と言えます。
ニュージーランドへの進出を検討する企業は、これらを総合的に評価し、自社の事業戦略との適合性を慎重に判断する必要があります。
NZ現地からみたリスク面についての考察
長年NZで起業や事業拡大に携わる身として、リスクNo.1とされた「人件費の高騰」と、No.5「従業員の離職率の高さ」についてコメントを加えたいと思います。
最大のリスク – 人件費の高騰
輸出を軸とする製造業であれば人件費の高騰は国際競争力の低下に繋がりかねませんが、今回調査を受けた日系企業の約66%が非製造業であり、事業拡大を意識している層の過半数がローカル市場ニーズの拡大を狙っているという事実を鑑みるなら、人件費の高騰は、NZ経済の構造上、過去数十年にわたりほぼ毎年起きている事。1980年代以降、現代に至るまでずっとインフレが進行し続けているNZは日本の対極にいると表現できるのでリスクとして捉えず日本とは市場構造が違うと理解してマインドセットを更新すべきです。
また非製造業でインフレが進行し続けるNZローカル市場をターゲットとする場合、日本とは異なり、NZの消費者はある程度のインフレを受け入れる土壌があるため人件費の高騰もある程度価格に転嫁しやすい傾向があると理解するとよいです。
従業員の離職率の高さ
NZでは一般的により良い条件(給与、役職、キャリアパス、ワークライフバランスなど)を求めて積極的に転職することを前提に、日本企業は従来の日本の雇用慣行に固執するのではなく、NZの雇用文化を理解し、それに適応した人事戦略を採用する必要があります。
ここで誤りがちなのが「そうであれば社員教育に力を入れない」という考えに辿り着くこと。
教育不足は従業員の自信を育まずに生産性や質を低下させ、ストレスを与えてエンゲージメントを下げ、離職率をより高める一因にしかなりません。
転職が活発なNZ労働市場=従業員は常に自身の市場価値を高めようとする傾向が強いとも言い換えられます。
だからこそ「どうせ辞めるから教育しても無駄」と考えるのではなく、「教育によって少しでも長く、そして高いパフォーマンスを発揮してもらい、組織全体の能力向上に繋げる」という視点を持つべきです。
教育機会を提供することは、常に自身の市場価値を高めようとする従業員のニーズに応えることになり、結果的に自社への定着を促す可能性があります。
「この会社にいれば、常に新しいスキルを習得し、自身の市場価値を高めることができる」と感じさせることが重要です。
売上高に占める比率
平均輸出比率
| 平均 | 36.8% |
| 100% | 12.2% |
| 75-100%未満 | 19.5% |
| 50~75%未満 | 7.3% |
| 25~50%未満 | 4.9% |
| 1~25%未満 | 9.8% |
| 輸出率 0% | 46.3% |
 ものかん
ものかんニュージーランドに進出している日系企業の約半数が輸出率0% =「ニュージーランドでの事業展開のみに注力している」という意味になります。今後1~2年の事業展開でローカル市場ニーズの拡大と答えた企業が多かったことと整合性がとれます。
輸出先の内訳
| 日本 | 54.5% |
| ASEAN | 5.0% |
| アメリカ | 3.2% |
| 中国 | 7.0% |
| オーストラリア | 15.5% |
| その他 | 11.3% |
【結論】ニュージーランド市場は「堅実・高付加価値志向」の場
JETROデータが示す通り
NZ市場は、「爆発的拡大を狙う市場」ではないので短期的な急成長を求める企業には適さないかもしれません。
しかし、安定した事業基盤の上で、ローカルのニーズに寄り添い、高付加価値な製品やサービスを提供することで、中長期的な堅実な成長と収益を目指す企業にとっては、「質と信頼性」を武器に中長期で着実に事業展開する市場として他に類を見ない魅力を持つ市場と言えると思います。
「堅実・高付加価値志向」こそが、NZ市場の真髄であり、進出を検討する企業が深く理解し、戦略に組み込むべき重要なキーワードとなるはずです。
ニュージーランド市場攻略3箇条
NZ市場で中長期的な成功を目指す日系企業は、以下3点を戦略に組み込むべきです。
1. ローカル消費者への最適化 × 高品質戦略
日本・他国の成功モデルをそのまま持ち込まず、NZ文化・消費者嗜好に合わせた製品・サービス最適化を図りつつ、「品質・信頼性」で勝負。
NZ消費者はコストパフォーマンス(価格とそこそこの品質)」を重視する傾向が強いが、その中で高付加価値・品質重視の商品は、適切なローカル適合と明確な価値説明があれば支持される余地がある。
*「日本品質の押し売り」は通じにくいため、価格と品質の最適バランス設計が必要。
2. 多様性を活かす人材戦略とエンゲージメント重視
NZの多様な人材を尊重し、個々の能力を最大限に活かす柔軟な雇用体制と、オープンなコミュニケーションに基づく信頼関係を構築する。その上で、従業員のキャリア志向を理解し、成長機会の提供を通じてエンゲージメントを高めることが、人材の定着と長期的な貢献に繋がる。ローカル企業との提携も視野に入れ、市場への浸透と効率的なオペレーション体制を確立する。
3. 短期利益より中長期的「堅実黒字」の許容
「爆発的成長はない」市場特性を理解し、損益均衡→安定黒字を目指す堅実経営を目指して進出・維持する。
データ:海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編) 日本貿易振興機構(JETRO)